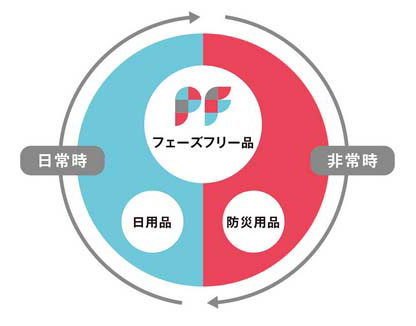身体と“もの”との関わり方を究明し、使いやすいデザインに生かしたい人々を笑わせ、そして考えさせる研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」。2022年の工学賞を受賞しました。主催者は受賞理由を「人間がつまみを回す際、最も効率的になる指の使い方の解明に挑戦した」としています。
人とものの間には規則性が隠れている
私が1996年に大学院へ進学した当初は、自転車のデザイン、特に折りたたみ自転車について研究をしていました。折りたたむ動作では、パイプのどこをつかんでどうたたむか、人の体と回転軸を持った物体との協調関係が大切です。しかし、研究テーマとしては複雑なもので、なかなか方向性を見出せずにいました。先生の指導もあり、生活の中で周囲を見渡してみると、音量調節のつまみや水栓金具など、つまんで回すものがたくさんあることに気づきました。今ではレバー式やタッチパネル、非接触のものも多いですが、当時はまだつまんでひねるものがたくさんありました。そこで、細い棒は2本でつまむけれど、少し太くなると3本で、もう少し太くなると4本で、さらに大きくなると5本指で回す、という誰もが行っている無意識の行為を数式や図で表せないか、と考えたのです。
被験者が直径の異なる円柱をつまんで回し、使った指の本数をプロットした図を作成しました。大きさはランダムに設置したので、まさに無意識の結果です。横軸がつまみの直径、縦軸がその指の本数を使う頻度。つまみの直径を大きくしていくと、ある直径から、それまで2本を使っていたのに突然3本を使い出すことが分かります。3本から4本へ変わる境目も分かりやすいのですが、4本から5本の境目はけっこうあいまいな人も多かったです。人によって傾向がいろいろありましたから、このグラフは「平均的な人」なんですけれども、どんな直径のものが何本指でつままれているのか、見えてきますね。このグラフを基に、原寸大のつまみモデル図も作成しました。これは、実際にデザインしたつまみをこの上に置いてみることで、人が自然につかむ指の位置に合っているかが一目で分かるようになっています。さらに、直径の変化と指の位置の関係を、中学校や高校で習うような二次関数で表しました。モデル図がなくてもこの式があれば、接触位置のモデル図が再現できるんです。その後、この実験結果による指の位置に合わせた溝をつけたつまみと、合わないように作ったものと比較し、それぞれの操作性や見た目のイメージについて検証しました。その結果、見た目がいいことと使いやすいことは別であるという結果を導き出しました。当たり前と言えば当たり前の結論ですが、これが後の博士論文につながりました。実験方法や論文の執筆にあたっては、共同受賞者の大内一雄先生、上野義雪先生、上原勝先生、井村五郎先生に大変お世話になりましたが、この受賞で少し恩返しができたような気がします。
地道に研究をしていたら……イグノーベル賞にノミネート?!
今回受賞した論文は、大学院時代に書いたものなんですよ。皆さんの卒業論文もそうだったと思いますが、特別なことをやったという意識はなく、あくまで地道にものづくりのための研究をした結果です。受賞の理由の一つは「誰も気にしないようなことをまじめに考えた」ところかなと想像しています。普段、何かをつまんで操作するときに「このノブはこれくらいの大きさだから、4本指でつまもう!」とは誰も考えませんよね。でも、ものを作る側はそこを考えなきゃいけないんです。デザインの研究をしている人は「こういう操作をするの であれば、こういう形にしたほうがいい」、「こういう指の使い方をすれば、こういう使いやすさにつながるのではないか」といつも考えています。「デザイン」というと芸術的なイメージを持たれる方も多いのですが、工学のデザインは、人とものの関係を追求するとても幅が広く奥の深い研究分野なんです。
人とものの間には規則性が隠れている
私が1996年に大学院へ進学した当初は、自転車のデザイン、特に折りたたみ自転車について研究をしていました。折りたたむ動作では、パイプのどこをつかんでどうたたむか、人の体と回転軸を持った物体との協調関係が大切です。しかし、研究テーマとしては複雑なもので、なかなか方向性を見出せずにいました。先生の指導もあり、生活の中で周囲を見渡してみると、音量調節のつまみや水栓金具など、つまんで回すものがたくさんあることに気づきました。今ではレバー式やタッチパネル、非接触のものも多いですが、当時はまだつまんでひねるものがたくさんありました。そこで、細い棒は2本でつまむけれど、少し太くなると3本で、もう少し太くなると4本で、さらに大きくなると5本指で回す、という誰もが行っている無意識の行為を数式や図で表せないか、と考えたのです。
被験者が直径の異なる円柱をつまんで回し、使った指の本数をプロットした図を作成しました。大きさはランダムに設置したので、まさに無意識の結果です。横軸がつまみの直径、縦軸がその指の本数を使う頻度。つまみの直径を大きくしていくと、ある直径から、それまで2本を使っていたのに突然3本を使い出すことが分かります。3本から4本へ変わる境目も分かりやすいのですが、4本から5本の境目はけっこうあいまいな人も多かったです。人によって傾向がいろいろありましたから、このグラフは「平均的な人」なんですけれども、どんな直径のものが何本指でつままれているのか、見えてきますね。このグラフを基に、原寸大のつまみモデル図も作成しました。これは、実際にデザインしたつまみをこの上に置いてみることで、人が自然につかむ指の位置に合っているかが一目で分かるようになっています。さらに、直径の変化と指の位置の関係を、中学校や高校で習うような二次関数で表しました。モデル図がなくてもこの式があれば、接触位置のモデル図が再現できるんです。その後、この実験結果による指の位置に合わせた溝をつけたつまみと、合わないように作ったものと比較し、それぞれの操作性や見た目のイメージについて検証しました。その結果、見た目がいいことと使いやすいことは別であるという結果を導き出しました。当たり前と言えば当たり前の結論ですが、これが後の博士論文につながりました。実験方法や論文の執筆にあたっては、共同受賞者の大内一雄先生、上野義雪先生、上原勝先生、井村五郎先生に大変お世話になりましたが、この受賞で少し恩返しができたような気がします。
地道に研究をしていたら……イグノーベル賞にノミネート?!
今回受賞した論文は、大学院時代に書いたものなんですよ。皆さんの卒業論文もそうだったと思いますが、特別なことをやったという意識はなく、あくまで地道にものづくりのための研究をした結果です。受賞の理由の一つは「誰も気にしないようなことをまじめに考えた」ところかなと想像しています。普段、何かをつまんで操作するときに「このノブはこれくらいの大きさだから、4本指でつまもう!」とは誰も考えませんよね。でも、ものを作る側はそこを考えなきゃいけないんです。デザインの研究をしている人は「こういう操作をするの であれば、こういう形にしたほうがいい」、「こういう指の使い方をすれば、こういう使いやすさにつながるのではないか」といつも考えています。「デザイン」というと芸術的なイメージを持たれる方も多いのですが、工学のデザインは、人とものの関係を追求するとても幅が広く奥の深い研究分野なんです。
私の研究は「無意識」というテーマに共通点があります。授賞式でも話したのですが、「鼻をつまんでください」というと、ほとんどの人は無意識に2本指でつまむんですよ。こんなふうに、ものに対して人が意識しないで行う動作や操作をじっくり観察して、デザインに生かしたいと思ってきました。
千葉工業大学同窓会「校友タイムス172号」より